東京から大阪に旅行で来る人は多いかと思いますが、中には転勤や新入学などで大阪に住むことになる人も多いと思います。
同じ日本であっても、東京で暮らすのと大阪で暮らすのにはいろんな違いがあります。一番わかりやすいのが言葉の違い(東京弁と大阪弁)と思いますが、それ以外にもいろんな違いがあります。
そこで、東京から大阪で暮らすことになった人が知っておきたい生活文化の違いについてお送りしたいと思います。今回はとくに「大阪での交通機関の使い方」についてまとめました。
東京と同じ感覚で生活したら、細かいところで違いがたくさんあることに気が付くかと思います。そんな中でも大阪に住むようになればすぐに気が付くと思われる交通機関の利用方法の違いについてまとめてみましたので、参考にしていただければと思います。
東京と大阪の交通機関の違い~バス編
東京も大阪も都会なだけにそれぞれ交通網は発達しています。
しかし大阪で生活するようになると、鉄道やバスなどの交通システムは東京と大阪では微妙に違うに気が付くかと思います。
まずはバスについてですが、この辺も東京と大阪では勝手が違うようです。
バスに乗るときは東京は前から乗り、大阪は後ろから乗る
東京でバスに乗るときは、基本前から乗ってそこでお金を払ってから乗り、降りるときは後ろのドアから降りるというスタイルです。
ですが大阪市(大阪シティバスの場合)でバスに乗るときは、後ろから乗って前から降りる形となります。これは東京以外のバス会社についていえるかと思いますが、大阪もこの例にのっとっています。
ただ東京も大阪も料金は定額なので、乗車するときにお金を支払っておけばどこまで乗ろうと金額は一緒なわけだから大阪も前から乗車して後ろで降りる形にしてもいいように思います。
ですがそうなっていないのは、やはり大阪市のバスが後ろから乗り前で降りるという形が昔から定着してあるので、一律定額になっていてもそうはなってない理由かもしれません。
大阪市では「大阪シティバス」一択
大阪市に限って言うと、大阪市内を走るバスはそのほとんどが「大阪シティバス」というもので、元々は大阪市交通局が運営していたバスが民営化したことで生まれたものです。したがって大阪市でバスに乗るときはほとんどこの薄緑色カラーのバスに乗ることになります。
東京の場合は、そういった一社独占ではなくていろんなバス会社のバスが走っていることからも、この点から見ても少し違和感があるのが分かります。
ただ大阪シティバスといってもたとえば「守口車庫(守口市)行き」「布施駅(東大阪市)行き」など周辺の他市に行くものも含まれています。また路線も数多くあって大阪市内の各地に行く路線があるので、大阪市内のほとんどの場所に行けるのも大阪シティバスの特徴といえます。
大阪シティバスの乗り方
大阪シティバスに乗るときは、後部の入口から乗車します。この際に現金支払い用の乗車券やICカード支払い用の端末にタッチということはしません。そのまま乗車してもらって大丈夫です。
降りる際は、停車ボタンを押してから降りることになりますが、このときに前の料金箱にお金を入れたり、ICカードでタッチしたりして料金を支払うことになります。
なお、現金支払いのときは、あらかじめ両替をしておいてからその乗車分の料金を支払う方式のバス会社が多いですが、大阪シティバスでは両替しなくても1000円や500円などを料金箱に入れれば勝手に精算されておつりが出てくるシステムになっています。
またICカードもSuicaやICOCAなどの交通系ICカードはほとんど使えますし、大阪では多くの方が持っている私鉄系のICカード「Pitapa」も大阪シティバスでは使えます。
ただPitapaはクレジットカードのように使った分を後で銀行口座の引き落としで支払うという方式のため、SuicaやICOCAといったチャージしてから使う交通系ICカードとは異なります。そのため全国のほかの地域のバスで利用するときは、「Pitapaは使用不可」であったり、「Pitapaにチャージしてから利用してください」という制約があります。
その点地元大阪ではPitapaで大阪シティバスの料金を支払うときも、事前にチャージとかしなくても普通に使えます。このほか細かい乗り方を知りたい方は、こちらの大阪メトロHPの「バスの乗り方」の記事をご覧ください。

東京と大阪の交通機関の違い~鉄道編
東京でも大阪でも鉄道については、JR、私鉄、地下鉄といったものがそれぞれ充実しています。
ですが東京と大阪の鉄道事情は少し異なります。たとえば次のようなものが挙げられます。
- 他社との相互乗り入れが東京は多いが、大阪は一部区間のみで採用される程度。
- 地下鉄は東京は東京メトロと都営地下鉄があるが、大阪はOsaka Metroだけ。
- 地下鉄は東京は複数の路線が入り乱れておりわかりにくいが、大阪の地下鉄は碁盤の目のように整備されていてとてもシンプル。
- JRにICカードで乗る場合、東京(JR東日本)では運賃は1円単位まで刻むが、大阪(JR西日本)は10円単位までしか刻まない。
- 鉄道で、東京は「2階建て車両」が走っているものがあるが、大阪では走っていない。
- 鉄道は、普通電車に有料座席がついている車両があるが、大阪ではついていない(※最近は大阪でもJR、私鉄で普通電車に有料座席を導入する動きがみられます。)
このような感じで東京と大阪の鉄道というだけでもこれだけの違いがみられます。
ただ総じていえることは、大阪の鉄道は東京ほど複雑ではなく、乗り換えなども比較的スムーズにできるように思います。
ICカードも「ICOCA」と「Pitapa」というものを用意しておけばほとんどのところで利用できますので、関西圏での鉄道やバスに乗るときはこの2つのカードのどちらかを用意しておくのがよいかと思います。
ただし先述したように、Pitapaは後払い方式でほかのICカードとは仕組みが異なり、東京などのほかの地域で利用するときはチャージしてからでないと使えないことが多いため注意が必要です。
なので、出張などでほかの地域でもICカードを使う機会が多い人は「ICOCA」、そうでなく関西圏だけでしかICカードを使わないという人は「Pitapa」というようにしてもいいかと思います。皆さんの事情に合わせて使い分けてもらえたらと思います。
その他関西圏での変わった交通機関
阪堺電車
阪堺電車は大阪市と堺市を結ぶ唯一の路面電車で、現在は南海電鉄の子会社である「阪堺電気軌道株式会社」が運営しています。
路線は「阪堺線」(恵美須町~浜寺駅前、約14.1km)と「上町線」(天王寺駅前~住吉、約4.6km)の2路線からなり、住吉で交差します。全複線で、大阪市南部から堺市へ全域に伸びる形です。
100年以上の歴史を持つ日本最古級の路面電車で、昭和レトロな雰囲気の車両も人気です。普通運賃は大人240円、小児120円となっており観光スポット巡りにも便利です。
大阪モノレール
大阪モノレールは、大阪都市圏の鉄道網を環状方向に結ぶために建設された日本で最も長い跨座式モノレール(レールにまたがって走る方式)です。
本線は大阪国際空港(伊丹空港)から門真市までを結び、さらに万博記念公園から彩都西までの「彩都線」も運行しています。
現在、さらに近鉄奈良線までの延伸工事が予定されており、2029年の完成を目指しています。
ニュートラム
大阪のニュートラムは、大阪市の南港ポートタウン線の愛称で、大阪市交通局(現在はOsaka Metro)が運営しています。
1981年に開業した日本で2番目に本格的に導入された自動運転の新交通システム(AGT)であり、無人運転で自動制御されています。
距離は7.9kmで、コスモスクエア駅から住之江公園駅の10駅を結び、海沿いの高架を走るための景色が良いのが特徴です。
車両はゴムタイヤで走行し、水色のラインカラーで親しまれています。 大阪メトロの他の地下鉄とは違い、地上を走る現代的な交通機関です。
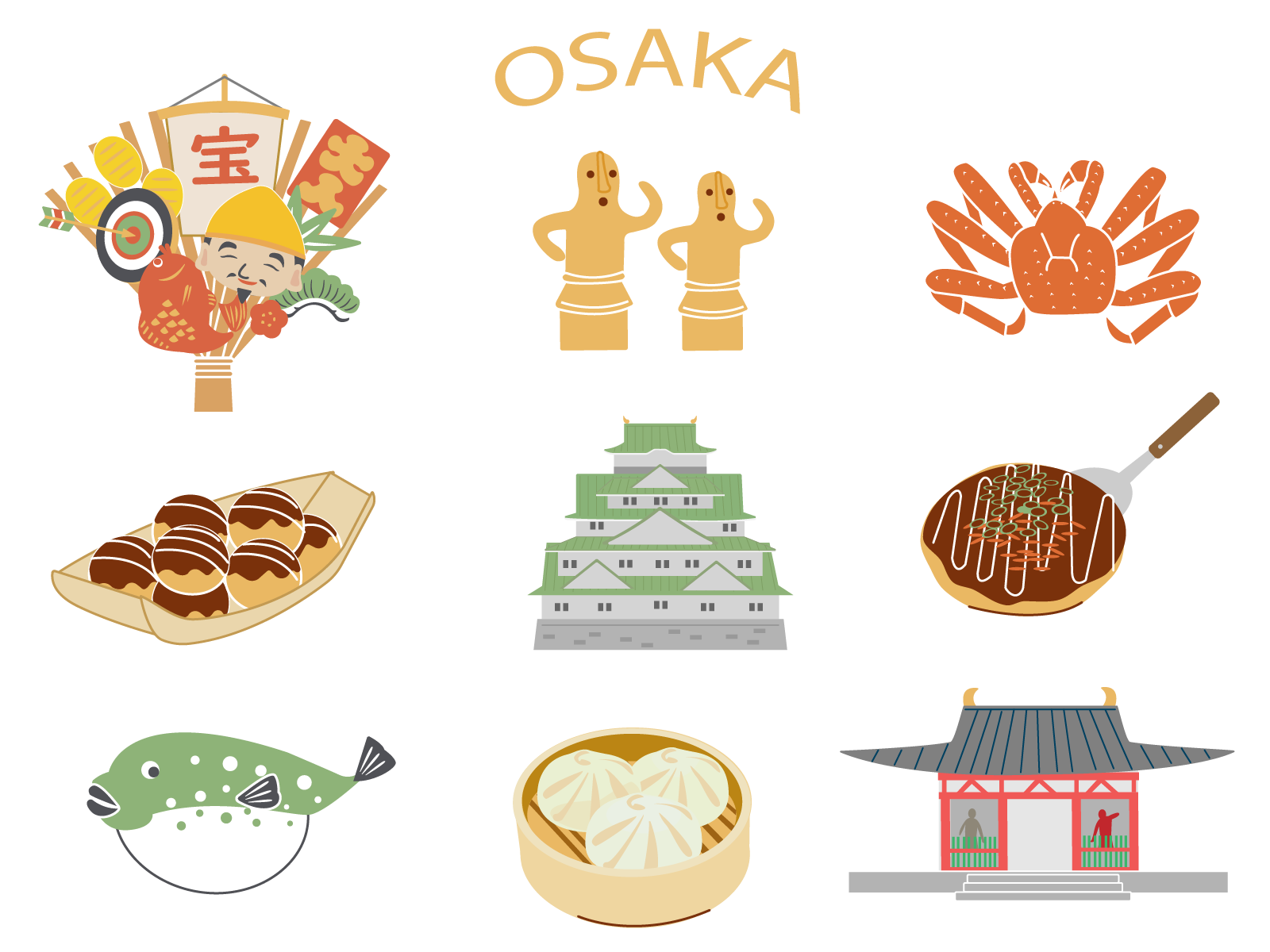


コメント